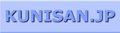電磁気学のABC - 電気と磁石の基本を勉強名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2012年1月13日 
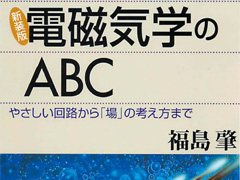 仕事の関係で電気と磁石についての基本的な知識を知っておいた方がよさそうな感じになってきたので、アマゾンで評価の良かった「電磁気学のABC 仕事の関係で電気と磁石についての基本的な知識を知っておいた方がよさそうな感じになってきたので、アマゾンで評価の良かった「電磁気学のABC私の大学時代の専攻は「工業化学」と理系でしたが、高校は進学校ではなかったため、理系の選択必修科目は化学のみしか取れず、物理については理系以外の人も必修の「理科I」(懐かしい…)の力学のところしかやりませんでした。さらに大学では遊び呆けていたため、物理も含めて勉強らしい勉強はやった記憶がありません(最後に英会話だけは勉強しましたが…)。 そのため、電気や磁石については、「電子の流れ」とか「磁性材料」とか、化学的な見地でしか捉えることができませんでした。しかし、磁力がプラズマに及ぼす影響とか、交流電流におけるコンデンサーの役割とか、電波の送受信の仕組みとか、そういったものの理解力に欠けていることに不満は感じていました。もう40歳間近なので、難しい公式などを改めて覚えるつもりは全くなかったのですが、電磁気学の概念的なところだけでも押さえておきたいという気持ちはありました。 「電磁気学のABC」ですが、最初は電池と電球の単純な直流回路の説明から入り、水流モデルを使って、電流、抵抗、電圧の「オームの法則」を視覚的に捉えられるように分かりやすく解説しています。それから、電流とエネルギー、電場と磁場、交流回路でのコンデンサーとコイルの役割、そして電磁波と、全てを繋ぐようにして話が展開していきます。 私はエネルギーの移動についても、物質の反応とか物体の移動とか、そういった見方に偏っていましたが、この本を読んで真空のような物質的には何も無い状態でも、エネルギーを運べる「場」というものが「あるものだ」ということがよく理解できました。 せっかくなので、この本の核になる法則を書いておきます(本書151ページ、173ページより抜粋)。 ・荷電粒子は湧き出し、吸込み型の電場を作る。 ・電流及び変動する電場は、その周りに循環型の磁場を作る。 ・単極の磁石は存在しない。 ・磁場の変化は循環型の電場を作る。 なお、電磁波とは「電場の変化は磁場を作る」と「磁場の変化は電場を作る」の組み合わせで、エネルギーが光と同じ速度で空間を伝わっていくもの、ということになります(光も電磁波の一種ですが)。 特定の電磁波と周波数を併せるため、コンデンサーの電気容量やコイルの長さで調節した回路を作成し、これにスピーカーや電気を一方向にしか通さないダイオードなどを入れることで、ラジオのような電波受信機が完成するということも理解できました。 そして、絶対零度にならない限り、物質中の分子・原子・電子は振動や運動を続けていて、それにより電磁波を放射しつづけているという説明も「なるほど」と思いました。温度が「振動」であることは化学的見地からも理解できますが、これと電磁気学が自分の頭の中で結びつけられたのは大きいです。まあ、あくまで入門書なので、その範囲で「わかったような気になった」というだけではありますが。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)

最近の記事: HandBrake - 動画ファイル一括変換ソフト / 笑って!ダミーちゃん - プチコン4でマイナーキャラの掘り起こしゲーム / Switch 2対応USB-Cハブ / Switch 2を購入 / あけましておめでとうございます(2026年) / インテリ君の英語遊び MLB中継編 - プチコン4で野球/ベースボール英語の学習ゲーム / A-TO-Z DASH - プチコン4でテキストベースのシンプルアクションゲーム / おばあさんが坂を駆け上がるゲーム - プチコン4でドリフの坂道コントをヒントにしたシンプルゲーム / ツインスティック・チェーン・ブラスト - プチコン4で連鎖爆発のシンプルSTG / ノックアウトドライブ - プチコン4でLRボタンだけを使ったショートゲーム
■ ホームへ
|