|
|

※該当の記事タイトル一覧はリンク一覧から参照できます。
SOEKS(ガイガーカウンター)-石神井公園周辺の放射線量測定名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2012年4月30日   Amazonでガイガーカウンター「SOEKS」 Amazonでガイガーカウンター「SOEKS」ガイガーカウンターを購入した理由ですが、「地域の安全を証明するため」とか「子供の健康を守るため」とかの深い意味ではなく、「興味本位」というのが最大の理由です。もちろん、昨年の福島原発の事故による放射性物質の飛散の影響を調べてみたい、というのも無くはないのですが、何よりも「自分で色々なデータを取りたい」というのが一番です。ただ、結果的に周辺の安全が確認できるのであれば、それに越したことはありません。 人が放射線を浴びる量については、シーベルト(Sv)で表されます。人間の健康に影響する可能性が出てくるのは、年間100ミリシーベルト(mSv)程度と言われていますが、このレベルでも放射線をほとんど浴びない場合と比較して、健康に対する影響は1%未満など「誤差の範囲内」とも言われています。また、地殻や宇宙などからも放射線が飛んでくることもあり(自然放射線)、普通に暮らしていても年間2.4mSv(世界平均)の放射線を浴びていることになるので、放射線ゼロというのはありえません。 放射線量の測定にあたってはガイガーカウンターが用いられますが、単位は「マイクロシーベルト/時(μSv/h)」で表されます。日本国内の1人あたりの線量は0.05~0.1μSv/h程度です(地域により異なります)。例えばこの10~20倍の1μSv/hの線量のところに1年間いたとして、1μSv/h x 24h x 365d ÷ 1000 = 8.76mSv/y(年間8.76ミリシーベルト)という計算になり、この程度でも健康に対する直接的な影響を観察できるレベルではありません。世界の中には、人が住んでいるようなところでも、これよりさらに高い放射線量の地域もあります。 飛行機に乗ると高度11,000mの上空で1.6μSv/h程度の線量になります。大雑把な計算ですが、日本-ヨーロッパ便に1~10回乗るとレントゲン1回分の線量、200~1000回乗るとCTスキャン1回分の線量と同等になります(レントゲンやCTスキャンについては、設備や測定箇所によって線量が異なります)。 ちなみに私の前職では「トリア入りタングステン」という材料を扱っていました。「トリア」というのは酸化トリウムのことで放射性物質です。当時はトリアから放射線が出ることも知っていましたし、ガイガーカウンターで放射線を検出したりもしていました(健康のために使うのではなく、ちゃんとトリアが入っているのかを調べる目的で使ってました)。ただ、「マイクロシーベルト」という単位や健康に対する影響などは意識したこともなく、10kg前後のトリア入りタングステンを目の前に、1時間程度ルーペや顕微鏡を使って表面検査を行ったりもしていました。 以下のページにトリア入りタングステンの線量測定結果(15.39μSv/h)が出ていますが、私はこの10倍以上の量のトリア入りタングステンを目の前に作業していたことになります。 http://amino-sangyo.com/free_9_3.html ただ、数ヶ月ぶっ続けで作業するなら健康に影響が出る可能性が出てくるのかも知れませんが(放射線よりストレスでやられてしまいそうですが)、私としてはこれを見て「1時間程度の作業なら、健康に全く影響は無かったのだろう」と今更ながら安心しています。あと、タングステンには放射線を遮蔽する効果もあるので、量が10倍になったとしても、単純に線量が10倍になるわけではありませんし、放射性物質から数十センチ距離があるだけでも、測定値に大きな差が出ます(放射線量は線源からの距離の2乗に反比例します)。 そのようなことで、私自身は放射線について「少しでもあったらダメ」と過敏に反応するわけではなく、「ちょっと位なら全く大丈夫」という心構えでいたりします。 前置きが長くなってしまいましたが、本題の放射線量測定結果は以下のようになりました。測定場所により数値のばらつきはありますが、いずれも健康に影響を及ぼすレベルではないので安心です。 ※放射線量の値は測定機器や測定方法によりばらつきが出ます。また、公的機関が設置しているモニタリングポストはγ線のみを検出するのに対し、今回測定した機械はγ線に加えてβ線も検出するタイプのため、単純に比較することはできません。以下の数値はあくまで目安です。  まず我が家(東京都練馬区のとあるマンション)のベランダで測定したところ、0.12μSv/hという値が出ました。鉄筋コンクリートの建物は材料自体に放射性同位元素を極微量含んでいることもあるので、少々高めではありますが、まあそれなりに納得できる値です。 まず我が家(東京都練馬区のとあるマンション)のベランダで測定したところ、0.12μSv/hという値が出ました。鉄筋コンクリートの建物は材料自体に放射性同位元素を極微量含んでいることもあるので、少々高めではありますが、まあそれなりに納得できる値です。 我が家のコンクリートの壁(壁紙付き)に置いて測定したところ、0.18μSv/hという値が出ました。やはり、コンクリートのそばは若干数値が高く出ます。 我が家のコンクリートの壁(壁紙付き)に置いて測定したところ、0.18μSv/hという値が出ました。やはり、コンクリートのそばは若干数値が高く出ます。 石神井公園ボート池の大気中の測定値は0.10μSv/hでした。 石神井公園ボート池の大気中の測定値は0.10μSv/hでした。 ボート池の近くの植物が植えられた所で測定したところ、0.19μSv/hでした。少々高めですが、そばにあるコンクリートが影響しているのかも知れません。 ボート池の近くの植物が植えられた所で測定したところ、0.19μSv/hでした。少々高めですが、そばにあるコンクリートが影響しているのかも知れません。 記念庭園の池のそば(ボート池の南のさらに道路を挟んだ南側)では、0.13μSv/hでした。 記念庭園の池のそば(ボート池の南のさらに道路を挟んだ南側)では、0.13μSv/hでした。 さらに記念庭園の池の近くにあった、木の根の雨水が留まりそうなところで測定したところ、0.19μSv/hでした。他の所より若干高い数値が出ていますが、注目するような値ではありません。 さらに記念庭園の池の近くにあった、木の根の雨水が留まりそうなところで測定したところ、0.19μSv/hでした。他の所より若干高い数値が出ていますが、注目するような値ではありません。 草地広場(石神井公園の南側の墓地の近く)の大気中の測定値は0.08μSv/hでした。 草地広場(石神井公園の南側の墓地の近く)の大気中の測定値は0.08μSv/hでした。 草地広場の土の上は0.09μSv/hでした。 草地広場の土の上は0.09μSv/hでした。 アスレチック広場(三宝寺池近く)は0.16μSv/hでした。子供が遊ぶ場所ですが、全く問題無いようです。 アスレチック広場(三宝寺池近く)は0.16μSv/hでした。子供が遊ぶ場所ですが、全く問題無いようです。 野球場(三宝寺池近く、井草通り沿い)のフェンスの近くは0.19μSv/hでした。 野球場(三宝寺池近く、井草通り沿い)のフェンスの近くは0.19μSv/hでした。石神井公園については測定する前から「大丈夫だろう」と思っていましたが、予想通りの結果でした。今度、海外出張の時にでも飛行機で上記のような数字(1.6μSv/h程度)が出るのか検証してみようと思います。 ちなみにこのガイガーカウンター 石神井周辺情報(リンク一覧): 来世は、きっとイタリア人 / スターバックスコーヒー エミオ石神井公園店 / 石神井とらの特製つけ麺(石神井公園) / うなぎ乃助 石神井公園店 / や台ずし 石神井公園町 / ...(記事連続表示) 関連カテゴリー: 石神井周辺情報, 科学・技術関連記事

電磁気学のABC - 電気と磁石の基本を勉強名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2012年1月13日  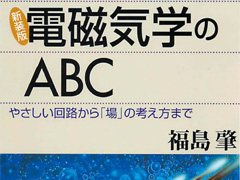 仕事の関係で電気と磁石についての基本的な知識を知っておいた方がよさそうな感じになってきたので、アマゾンで評価の良かった「電磁気学のABC 仕事の関係で電気と磁石についての基本的な知識を知っておいた方がよさそうな感じになってきたので、アマゾンで評価の良かった「電磁気学のABC私の大学時代の専攻は「工業化学」と理系でしたが、高校は進学校ではなかったため、理系の選択必修科目は化学のみしか取れず、物理については理系以外の人も必修の「理科I」(懐かしい…)の力学のところしかやりませんでした。さらに大学では遊び呆けていたため、物理も含めて勉強らしい勉強はやった記憶がありません(最後に英会話だけは勉強しましたが…)。 そのため、電気や磁石については、「電子の流れ」とか「磁性材料」とか、化学的な見地でしか捉えることができませんでした。しかし、磁力がプラズマに及ぼす影響とか、交流電流におけるコンデンサーの役割とか、電波の送受信の仕組みとか、そういったものの理解力に欠けていることに不満は感じていました。もう40歳間近なので、難しい公式などを改めて覚えるつもりは全くなかったのですが、電磁気学の概念的なところだけでも押さえておきたいという気持ちはありました。 「電磁気学のABC」ですが、最初は電池と電球の単純な直流回路の説明から入り、水流モデルを使って、電流、抵抗、電圧の「オームの法則」を視覚的に捉えられるように分かりやすく解説しています。それから、電流とエネルギー、電場と磁場、交流回路でのコンデンサーとコイルの役割、そして電磁波と、全てを繋ぐようにして話が展開していきます。 私はエネルギーの移動についても、物質の反応とか物体の移動とか、そういった見方に偏っていましたが、この本を読んで真空のような物質的には何も無い状態でも、エネルギーを運べる「場」というものが「あるものだ」ということがよく理解できました。 せっかくなので、この本の核になる法則を書いておきます(本書151ページ、173ページより抜粋)。 ・荷電粒子は湧き出し、吸込み型の電場を作る。 ・電流及び変動する電場は、その周りに循環型の磁場を作る。 ・単極の磁石は存在しない。 ・磁場の変化は循環型の電場を作る。 なお、電磁波とは「電場の変化は磁場を作る」と「磁場の変化は電場を作る」の組み合わせで、エネルギーが光と同じ速度で空間を伝わっていくもの、ということになります(光も電磁波の一種ですが)。 特定の電磁波と周波数を併せるため、コンデンサーの電気容量やコイルの長さで調節した回路を作成し、これにスピーカーや電気を一方向にしか通さないダイオードなどを入れることで、ラジオのような電波受信機が完成するということも理解できました。 そして、絶対零度にならない限り、物質中の分子・原子・電子は振動や運動を続けていて、それにより電磁波を放射しつづけているという説明も「なるほど」と思いました。温度が「振動」であることは化学的見地からも理解できますが、これと電磁気学が自分の頭の中で結びつけられたのは大きいです。まあ、あくまで入門書なので、その範囲で「わかったような気になった」というだけではありますが。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)

レアメタル・レアアース - 雑誌ニュートン名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2011年1月29日  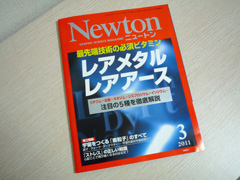 久しぶりにNewton (ニュートン) 久しぶりにNewton (ニュートン)レアメタルとは存在量が少なかったり、抽出するのが困難だったり、入手するのが難しい金属の総称です。レアアースも全てレアメタルの中に含まれます。ちなみに、レアメタルは和製英語で、英語では「minor metal(s)」と呼ばれます。レアアースはそのまま英語で「rare earth(s)」です。 今回ニュートンではリチウム(Li)、白金(Pt)、ネオジム(Nd)、ジスプロシウム(Dy)、インジウム(In)の5種類のレアメタルが詳しく紹介されています。技術的な詳細については、ニュートンを読んでいただくとして、これらの金属について個人的な知識や思い出を書いておこうと思います。 ■ リチウム リチウムと言えば、周期表の左上の方にあって、「ナイフでも切れる柔らかい金属」という印象があります。最近ではリチウムイオン電池としての用途が多く、リチウムの名前を聞いたことが無い人はいなのではないかと思います。リチウムは密度が低く(0.53g/cm3)、水にも浮くほどなのですが、実際には水に触れるとすぐに反応して、水素を発生しながら水酸化リチウム水溶液となります。 ■ 白金(プラチナ) 白金に初めて触れたのは、大学の実験の時でした。金属の炎色反応を観察するのに、割り箸程度の長さの棒の先に、白金のリングが付いた器具を使いました。これを金属イオンが溶け込んだ水溶液に浸した後、バーナーの炎に近づけると特有の色の炎色反応を見ることができます。白金を使うのは他の物質との反応性が非常に低いことと(水溶液や炎の熱でも反応しない)、融点が高いこと(同じく反応性の低い金よりも700℃程度高い)があります。 その後、婚約指輪・結婚指輪までは、白金に触れることはありませんでした。 白金の用途としては、主に排ガス浄化装置や燃料電池などの触媒用として使われています。 ■ ネオジム、ジスプロシウム ネオジム、ジスプロシウムのどちらもレアアースです。「ネオジム」はよく「ネオジウム」と誤記されていますが、驚くことにGoogleで検索すると、「ネオジム」は185,000件、「ネオジウム」は352,000件と、「ネオジウム」の方が件数が多くなっています。日本語のネオジムはドイツ語の「Neodym」から来ており、英語も「Neodymium」なので、国際的に「ネオジウム(Neodium?)」では通じません。 携帯のバイブレーターやハードディスクに使われるなど、小型でも磁力が非常に強いネオジム磁石ですが、他の種類の磁石に比べて、高い温度で磁力が落ちるという欠点がありました。これを改良したのが、ネオジム磁石にジスプロシウムを加えた磁石です。 ただ、ネオジムにしても、ジスプロシウムにしても、直接手に触れたことはありません。 レアアースは全般的に酸素と結びつきやすい性質を持っているので、単体(金属)の状態で目にすることは稀と言えます。 ■ インジウム インジウムは液晶ディスプレイや太陽電池に使われるITO(酸化インジウムスズ)の原料として大量に消費されています。日本は中国などからインジウムを大量に輸入していますが、そのほとんどがITO製造用です。 インジウムの融点は157℃と金属の中では極めて低く、例えば火にあぶったフライパン程度の熱でも溶けてしまいます。その性質を利用して、スパッタリングターゲット(成膜用の金属の板)をバッキングプレート(スパッタリングターゲットをスパッタ装置に取り付けられるようにするための部品)に取り付ける際に、「糊」のような役割で使うこともあります(正確にはボンディング材と言います)。私が金属インジウムを初めて目にしたのは、こちらの「糊」の用途でした。 他にも仕事で色々なレアメタルを目にしましたが、もちろんまだ見たことのないものもあります。個人的にはオスミウム、イリジウムに触れてみたいです。どちらも金よりも大きな比重を持っています。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)

石神井公園駅のそばで見えた虹名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2009年7月19日   今日の夕方、たまたま石神井公園駅南口の近くにある大鷲神社に寄ったところ、はっきりとした虹が見えました。右端と左端が繋がっていない、部分的な虹でしたが、これだけはっきりとしたものを見たのは久しぶりです。駅周辺の雑踏とした風景に、夕暮れの虹…。悪くないですね。 今日の夕方、たまたま石神井公園駅南口の近くにある大鷲神社に寄ったところ、はっきりとした虹が見えました。右端と左端が繋がっていない、部分的な虹でしたが、これだけはっきりとしたものを見たのは久しぶりです。駅周辺の雑踏とした風景に、夕暮れの虹…。悪くないですね。よく夕焼けと並んで、夕暮れの虹も「天気が良くなる」と言われています。虹は常に太陽の反対側に現れます。特に夕方にひと雨あり、西の空が晴れているときなどは、東の空に虹が出やすくなります。偏西風の影響で雲は西から東に流れることが多いので、西の空が晴れているということは(つまり夕方東の空に虹が出るということは)、これから天気がよくなる可能性が高いということになります。昔の人も経験から分かっていたんでしょうね。 ところで今日の虹は外側にもうっすらとした虹がある「ダブル虹(ダブルレインボー)」でした(写真には写っていませんが)。海外ではニュージーランドやケニアでも見たことがありますが、日本で見るのは初めてでした。普通の虹は内側から紫→青→黄→赤に徐々に変色しますが、ダブル虹のもう一方(外側にある暗い方)は赤→黄→青→紫と順番が逆になります。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)
コメント:石神井公園駅のそばで見えた虹 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2009年7月19日   参考までに…。 参考までに…。2001年にケニアで撮影したダブル虹です。 
基礎からよくわかる偶然の数学「確率」-雑誌ニュートン名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2009年6月27日  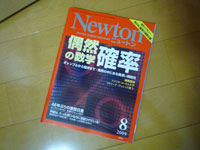 私がパソコンのプログラミングを始めたのは小学6年生の時でした。特にゲームを作成するのが大好きで、よくミニゲームを作っては友人に遊んでもらい、「面白い」と言ってくれるのを聞くのが楽しみでした。 私がパソコンのプログラミングを始めたのは小学6年生の時でした。特にゲームを作成するのが大好きで、よくミニゲームを作っては友人に遊んでもらい、「面白い」と言ってくれるのを聞くのが楽しみでした。ゲーム制作に重要な要素の一つとして「乱数」が挙げられます。乱数と条件式を組み合わせることにより、「確率」の要素が発生します。飽きないゲームというのは、この確率のバランスがよく取れていると言っても過言ではないでしょう。 そんな経験もあってか、高校時代は数学の「確率・統計」が得意でした。進学校ではなかったこともあり、授業として受けたことはなかったのですが、大学受験の模擬試験などでは一度も間違えたことがないほど得意な科目でした。 「確率はギャンブルが生み出した学問」とも言われています。確かに競馬、パチンコ、麻雀などのギャンブルは、確率論と切っても切り離せない関係です。しかし、確率論はギャンブルやゲームにとどまらず、気象、経済、製造、金融など、さまざまな種類のビジネスで重要な役割を担っています。天気予報の降水確率、為替や株価などの予測、工場の製品不良発生率、生命保険の掛け金設定…、など、確率論なしには成り立ちません。 そういうことで、久しぶりに確率論の本(ニュートン2009年8月号) さて、ここで問題です。 ある家族には子供が2人います。そのうちの1人は男の子であることがわかりました。では、もう1人も男の子である確率は? 答えは1/2(50%)…、ではなくて1/3です。 もし問題が、「男の子がいる家族がいます。そのお母さんが2人目の子供を妊娠しています。お腹の中の子が男の子である確率は?」なら1/2という答えになります。違いを理解できますか? さらに、「子供2人組を何組も集めるとします。そのうち1組をピックアップするとして、これが男の子2人組みである確率は?」という問題はどうでしょう?答えは1/4です。 理解できない方は、早速 ニュートン2009年8月号 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)

新・太陽系 - 雑誌ニュートン名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2009年3月8日  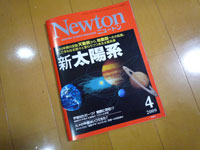 今回のニュートンのお題は「新・太陽系 今回のニュートンのお題は「新・太陽系まず、従来「エッジワース・カイパーベルト」と呼ばれていた海王星の軌道の外に多数存在する小天体ですが、これは現在では「太陽系外縁天体」と呼ばれているそうです。「エッジワース…」が古い呼び名になっているなんて知りませんでした。この太陽系外縁天体には、あの冥王星やエリス(冥王星より少し大きい)も含まれます。冥王星やエリスのような球体の天体は、軌道の関係から惑星には分類されないものの、2006年より「準惑星」と呼ばれることになっているようです。 その太陽系外縁天体は、現在では数百個も発見されています。しかし、今年から始まる「パンスターズ計画」という、口径1.8メートルの望遠鏡に、ブレ補正機能の付いた14億画素ものカメラを使って、動く天体を観測する、という手法を用いることにより、1万以上の太陽系外縁天体を発見することが期待されています。この他にも、多数の小惑星や彗星などが見つかることも期待されています。さらには未知の惑星の発見も…。 まだまだ太陽系にもわからないことは沢山あるのでした。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)

やさしくわかる…?相対性理論名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2008年6月27日  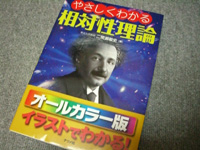 高校生の時に相対性理論の入門書を購入して以来、10年以上ぶりに相対性理論の本を買ってみました。タイトルは『やさしくわかる相対性理論 高校生の時に相対性理論の入門書を購入して以来、10年以上ぶりに相対性理論の本を買ってみました。タイトルは『やさしくわかる相対性理論相対性理論はアインシュタインが提唱した理論で、量子論とならぶ物理の二大理論のうちの一つです。相対性理論には特殊相対性理論と一般相対性理論の2つがありますが、比較的イメージしやすい方の特殊相対性理論で、よく知られている現象にはこんなものがあります。 ・光速はどの速度で見ても光速にしか見えない。 ・光速に近づくほど時間の進みが遅くなる。 ・光速に近づくほど重量が重くなる。 ・光速に近づくほど長さが縮む。 ・1gの質量は石油20万リットルを燃焼させる場合のエネルギーに等しい。(核燃料や核爆弾に応用されています) 具体的には、例えば地上から光速に近い速度で動いているものの時間は遅く進んで見えるのですが、その光速に近い速度で動いている物体から地上を見ると、地上の時間の方が遅く進んで見えるのです。このあたりは少々理解しづらいところではありますが、「相対性」の名前の通り、運動や時間は全て相対的なものとして考えられています。 これに重力がからんでくる一般相対性理論は、常人ではさらに理解しづらいもので、さらに理論を発展させた宇宙論や「10次元の時空」などは、その世界を想像するには超人的な能力が必要なのではないかと思わせるほどです。 普通に生活する上では何の関係もなさそうな相対性理論ですが、カーナビ技術、原子力発電、先端医療などに応用されているのです。アインシュタイン様さまですね。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)

宇宙論 - 雑誌ニュートン名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2008年6月1日  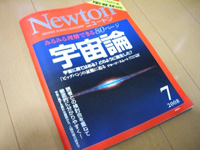 久しぶりに雑誌ニュートンを購入しました。今回のお題は「宇宙論」。宇宙と言っても、スペースシャトルや火星、太陽、月などの(比較的)身近なものではなく、宇宙の誕生や宇宙の果てなどの、「世界の成り立ち」の根源に関わる理論です。世界の始まりや世界の果てについては、哲学や宗教などでも扱われる議題ですが、ここでの宇宙論は計算と観測によって得られた結果をもとにした理論や推測です。ここ数年の観測技術の急速な発達によって、宇宙論もより精度が高まり、中には以前と内容が変わってしまっているものもあります。 久しぶりに雑誌ニュートンを購入しました。今回のお題は「宇宙論」。宇宙と言っても、スペースシャトルや火星、太陽、月などの(比較的)身近なものではなく、宇宙の誕生や宇宙の果てなどの、「世界の成り立ち」の根源に関わる理論です。世界の始まりや世界の果てについては、哲学や宗教などでも扱われる議題ですが、ここでの宇宙論は計算と観測によって得られた結果をもとにした理論や推測です。ここ数年の観測技術の急速な発達によって、宇宙論もより精度が高まり、中には以前と内容が変わってしまっているものもあります。例えば宇宙の誕生時に起こったとして考えられている「ビッグバン」ついては、私が以前に見た資料では「約200億年前」ということが書いてあったと記憶しています。しかし最近では「137億年前」と、かなり正確な数字になっています。 宇宙は膨張しつづけているという「ハッブルの法則」は、観測でも「遠い天体ほど、より早い速度で遠ざかっている」ということがわかっていて、これを逆にとると、以前これらの天体は、1点に集約していた可能性が高いということが推測されていました。 しかし、ビッグバンは本当にあったのでしょうか?色々な反論がありますが、分かりやすいのは「もしかしたら宇宙は膨張と縮小を繰り返したのかもしれない。今はたまたま膨張のタイミングでは?」ということです。 しかし、最近「宇宙背景放射」がかなり正確に観測されたことにより、これがビッグバンの確たる証拠としてみなされるようになりました。「宇宙背景放射」は地球から137億光年のかなたからやって来るマイクロ波です。このマイクロ波は137億年前のビッグバンのなごりです。つまりビッグバンから137億光年離れた地球で、137億年前のビッグバンそのものとも言える「宇宙背景放射」がリアルタイムに観測できるのです(文章では説明しづらいので、興味のある方はニュートンを買ってください)。 宇宙の果てについては、「果てはない」ということになっているようです。観測可能な領域は地球から137億光年先(つまり宇宙背景放射が観測されるところ)ですが、それ以上先の天体については、地球から見て光速以上の速度で遠ざかっているため地球に光が届くことはありません(この先、宇宙が縮むことがあれば話は別でが)。なぜ「果てはない」と言えるのかと言うと、科学的な根拠からではなく、「果てがあるとすると『その向こうは何か』と考えざるとえず、理論的におかしなことになるから」という形而上学的な思考によるものです。 もう一度ビッグバンの話にもどしますが、ビッグバンについても「宇宙のはじまり」としてしまうと、「それより前は何があったのか?」と考えざるをえません。そのため、ビッグバンは「膨張する灼熱の初期宇宙」とだけ考える場合があるようです。中には宇宙が空間も時間もない「無」から生まれたという仮説がありますが、もちろんこれは観測から得られた100%根拠のある理論ではありません。ただ、量子論では真空状態からエネルギーによって物資が作られるということが実験でも証明されていて、この理論に手を加える形でなんらかの発展があるかも知れません。いずれにしても、一歩間違えると何だか宗教じみた理論で面白いです。 その他、まだよく知られていない「ダークマター」「ダークエネルギー」などの記述もあります。とにもかくにも、人間にとって宇宙は広すぎます。そんな宇宙を計算と観測だけで解析していく宇宙学者もすごいものです。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示)

磁石 - 雑誌ニュートン名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2007年10月10日  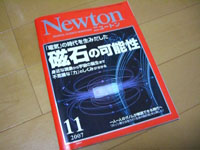 久々に雑誌『ニュートン』を購入しました。今月のお題は「磁石」。今では冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、携帯電話、掃除機、ハードディスク…など、数多くの電気製品に当たり前のように磁石が使われていますが、そんな「磁石」が原子&電子レベルでどのようなものなのかを解説してます。 久々に雑誌『ニュートン』を購入しました。今月のお題は「磁石」。今では冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、携帯電話、掃除機、ハードディスク…など、数多くの電気製品に当たり前のように磁石が使われていますが、そんな「磁石」が原子&電子レベルでどのようなものなのかを解説してます。面白いな、と思った内容を数点ピックアップしてみます。 ・「ネオジム磁石」なら、きゅうり、玄米、シャーペンの芯が動かせる。 →強力な磁力により、水分や微量の鉄分なども反応するそうです。 ・磁石を高温で熱すると、磁力を失う。 →実際に磁石をコンロで熱して、クリップが落ちている写真があります。 ・地磁気(地球のN極とS極)は数千年~数十万年おきに逆転する。 →方位磁針が南北逆転するなんて信じられますか? … 電磁気を専門に勉強されている方などにとっては何でもないことなのでしょうけど、私には衝撃的な事実でした。 「原子の種類」と「磁性の有無」の関係については、私も昔から疑問に思っていましたが、現代の学者でも強磁性の理由を説明するのは難しいようですね。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示) 
高校の化学の参考書名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2007年4月11日  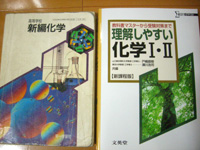 もう6~7年も前から「化学英語の基礎」のようなホームページを作りたいと思っていたのですが、先日ようやく高校の化学の参考書を手に入れて、少しだけやる気になったところです。 もう6~7年も前から「化学英語の基礎」のようなホームページを作りたいと思っていたのですが、先日ようやく高校の化学の参考書を手に入れて、少しだけやる気になったところです。高校時代は化学が一番の得意教科で、授業より先に自分で教科書を読み進めていったほどでした。大学の専攻もそのまま化学だったのですが、以来まともに化学を勉強した事はありませんでした。 まず驚いたのが、今は「化学Ⅰ」、「化学Ⅱ」と分かれているんですね。私が高校の頃は「化学」の一教科しかありませんでしたが、当時の教科書を前半と後半に分けているわけではなく、部分部分をⅠにしたりⅡにしたりしているような感じです。「これで体系的に学習できるのかな?」と不安に感じたりしますが、これもゆとり教育の一環なのでしょうか?よくわかりません。 あと、一部単位が変わっているものがあり新鮮でした。気体の圧力はatm(アトム)→kPa(キロパスカル)、熱量はkcal(キロカロリー)→kJ(キロジュール)に変更になっていました。高校化学の世界もSI単位(国際単位)の流れを組むようになったんですね。 それにしても高校時代に得意だった教科の参考書を見るというのは面白いものです。「これやったなあ」とか「こんなのあったっけ?」とか思ったり、当時の学習風景を思い出したりもしてしまいます。 逆に当時苦手&嫌いだった「世界史」だったりしたら、たぶん当時のことを思い出したりはできないのでしょう。でも、いくつも海外旅行を経験した今なら、もう少し楽しく勉強できそうな感じがします。 「古文や漢文も、もう少したてば興味を持てるのかな?」と考えたりしてます。 科学・技術関連記事(リンク一覧): 病名を英語で / 天然(自然)のセシウム(Cs)とストロンチウム(Sr)と合金と化合物 / Crash Course Astronomy - YouTubeで天文学&英語学習 / 宇宙を知る - 知恵袋BOOKS / 甲種危険物取扱者試験の合格を目指して / ...(記事連続表示) コメント:高校の化学の参考書 名前: みやけ 日付: 2007年4月12日  化学ですか!!懐かしい!!もう遠ざかっています!! ただ、なんか今の会社に入って物理を勉強しているような感じです!! 単位は、確か俺の大学時代が入れ替わりのじきだった気がします!! そういえば、関数電卓とか使いませんでした!? 俺は、当時苦手だった英語も昔よりは好きになりました!!ということで、明後日から4日間台湾へ行ってきます!!マイルつかっての一人旅です!!もちろん、英語も使ってきます!! コメント:高校の化学の参考書 名前: 小川 邦久 リンク: http://kunisan.jp/ 日付: 2007年4月12日  大学時代は関数電卓の変わりにポケコン使ってました。詳しいことは忘れましたが、統計計算の他、対数関数やべき乗の計算に多用した記憶があります。
台湾気をつけて行ってきてくださいね。食べ物がおいしいので、食べ過ぎにご注意を! 
※該当の記事タイトル一覧はリンク一覧から参照できます。
■ ホームへ
|
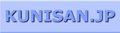


![Newton (ニュートン) 2011年 03月号 [雑誌]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gBRwgiaSL._SX298_BO0,204,203,200_.jpg)

![Newton (ニュートン) 2009年 08月号 [雑誌] (雑誌)](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Xb7JsOdxL._SX298_BO0,204,203,200_.jpg)
![Newton (ニュートン) 2009年 04月号 [雑誌] (雑誌)](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51gDUb3N7TL._SX298_BO0,204,203,200_.jpg)

![Newton (ニュートン) 2008年 07月号 [雑誌] (雑誌)](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51MOdhaoPXL._SX298_BO0,204,203,200_.jpg)